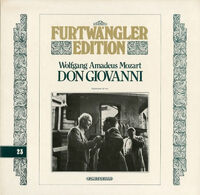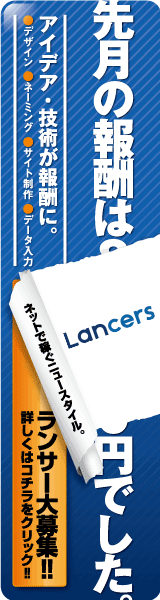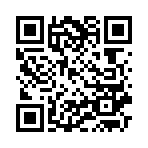「クラシック音楽専科ガイド」
オリジナル稀少盤、アナログ・レコード優秀録音盤のアナログサウンド!
オリジナル稀少盤、アナログ・レコード優秀録音盤のアナログサウンド!
1960年代、70年代、80年代までのクラシック音楽のアナログLPレコードの、欧米で発売された当時の『オリジナル盤』初版盤、レアなレコードぞろい。優秀録音と評価の高い録音をメインにコンディションの良いものを案内しています。
2020年07月05日
寂寥と結晶化した★フルトヴェングラー ウィーン・フィル モーツァルト 交響曲40番&アイネ・クライネ・ナハトムジーク
フルトヴェングラーの魂の告白 ― 涙の追いつけないテンポこそが壊滅を目前にしたドイツにふさわしい挽歌だ。
 《東芝音楽工業株式会社盤》JP 東京芝浦電気 HA1018 フルトヴェングラー ウィーン・フィル モーツァルト 交響曲第40番/セレナーデK.525 第2次世界大戦時中もドイツに残り、ひとり指揮をし続けたという大指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1986〜1954年)。戦時中の1944年1月のベルリン大空襲の際、ベルリン・フィルの当時の本拠地だった旧ベルリン・フィルハーモニーホールは炎上し焼け落ちてしまった。そのため以降の演奏会は、アドミラル・パラストで行われていた。ここは戦禍を逃れ、大戦前の建物としてベルリンでは数少ない貴重な建物として残っている。戦後は、同じく建物を失ったベルリン国立歌劇場管弦楽団が、本拠地再建後の1955年に再開するまで、ここで演奏会とオペラの上演を行った。戦後まもなくメニューインを迎えて、ユダヤ人コミュニティーを支援するチャリティーコンサートを開いている。
《東芝音楽工業株式会社盤》JP 東京芝浦電気 HA1018 フルトヴェングラー ウィーン・フィル モーツァルト 交響曲第40番/セレナーデK.525 第2次世界大戦時中もドイツに残り、ひとり指揮をし続けたという大指揮者ヴィルヘルム・フルトヴェングラー(1986〜1954年)。戦時中の1944年1月のベルリン大空襲の際、ベルリン・フィルの当時の本拠地だった旧ベルリン・フィルハーモニーホールは炎上し焼け落ちてしまった。そのため以降の演奏会は、アドミラル・パラストで行われていた。ここは戦禍を逃れ、大戦前の建物としてベルリンでは数少ない貴重な建物として残っている。戦後は、同じく建物を失ったベルリン国立歌劇場管弦楽団が、本拠地再建後の1955年に再開するまで、ここで演奏会とオペラの上演を行った。戦後まもなくメニューインを迎えて、ユダヤ人コミュニティーを支援するチャリティーコンサートを開いている。1945年1月23日、フルトヴェングラーのベルリンでの戦中最後の演奏会がアドミラル・パラストで開かれた。連合軍の激しい空襲がいつやってくるか分からない、そんな状況でのコンサート。プログラムは、モーツァルトの「魔笛」序曲、交響曲第40番。そして、ブラームスの交響曲第1番であった。
「魔笛」序曲の次に控える曲は、フルトヴェングラーにとって例外的に厄介な交響曲第40番だった。巨匠は背筋を伸ばし、ステージに向かって力強く歩みを進めた。会場は割れんばかりの拍手で満ちた。顔の前に構えた指揮棒が暫時ためらうように震えていたが、やがて空を斬り、冒頭の分散和音の緊迫した、さざ波をヴィオラ群が奏で、すぐにヴァイオリン群がモーツァルトが書いた旋律の中でも白眉な名旋律を歌い出した。
それはスタンダールの言う“甘美な憂愁”ではなく、寂寥と結晶化した悲哀をフルトヴェングラーは表出させる。この誰よりも速く疾走する、涙の追いつけないテンポこそが壊滅を目前にしたドイツにふさわしい挽歌だと、この時の巨匠にとって、この曲の本質であるべきだった。
交響曲第40番は第1楽章を終え、第2楽章が演奏され始めたところで空襲警報が鳴り突如ホールの照明が消える。薄暗い非常灯の中で演奏は、しばらく続いたが、やがて力尽きるように旋律は絶たれる。団員も観客もまんじりともせず事態を見守った。何が起きてもおかしくない状況だったが、誰も席を立とうとしなかったという。それから1時間後、公演は再開された。
曲はモーツァルトではなく、後半に予定されていたブラームスの交響曲第1番。残念ながら全曲が録音されることはなかったが、誰かの意地だったのだろう、ブラームスの交響曲第1番の終楽章だけが残されている。その演奏後の拍手が尋常じゃなく、終楽章の演奏がどうこうではなく拍手のためにある録音だ。そのおそろしい状況下での演奏は、聴く者の想像を絶する。「命がけ」とか「死と隣り合わせ」とか、そうした言葉の形容が軽く感じられる。鑑賞とは別の次元の体験をさせられることになるフルトヴェングラーの演奏の記録の中でも最も特殊な演奏のひとつだ。
停電が復旧後にフルトヴェングラーは中断したモーツァルトを続けなかったのは何故か、おそらく停電でフルトヴェングラーの心中が変生したのだろう。間もなく彼はスイスへ亡命することとなる。その翌朝、彼はヒトラー暗殺未遂事件への関与で何時逮捕されても不思議ない状況であることを友人から告げられる。折しもウィーンでのコンサートが予定されていたので、これを理由に、この日のコンサートが終わるとすぐ夜行列車に乗り、プラハ経由でウィーンに向かった。結果ベルリンの友人・同僚、そして、彼のオーケストラであるベルリン・フィルハーモニーにも何も告げずにベルリンを去った。
ウィーンに着いたのは翌25日のことである。この日は彼の59歳の誕生日であった。今度は、彼はウィーンでちょっと転んで怪我をしたのを理由に、その後のベルリンでのコンサートをキャンセルしてスイスに渡り、いくつかのコンサートを指揮する。これらがフルトヴェングラーの戦中の最後のコンサートとなってしまった。1945年1月23日。この日の公演は午後3時から始まった。夜は空襲があるからという理由だ。そして、この日の連合軍の爆撃音を聞くことができる。ベルリンの人々の音楽への狂気ともいえる情熱を感じるのだが、この1月23日にはギーゼキングによる「皇帝」のコンサートが開かれており、そのときの録音が残っていて、そこに爆撃音がはっきりと残っているのである。フルトヴェングラーがベルリンを去っても、ベルリン・フィルはコンサートを続行した。
戦中最後のコンサートは1945年4月16日に行われた。それから2週間後にヒトラーは自殺し第二次大戦は終焉を告げる。フルトヴェングラーが彼のオーケストラを残して一人旅立つ断腸の思いの籠った、この「音」が頭の中からどうしても消えない。そして聴衆は一体どういう思いでこの「拍手」をしたのか。この拍手には楽団員の気持ちも含まれているだろう。それを想像すると、ぞっとする。それは、第二次世界大戦後の「ト短調交響曲」の演奏にまったく影を投げかけていないとは考えられない。戦後唯一のベルリン・フィルの定期は、1949年6月のことであり、名演として知られるウィーン・フィルとの録音は、その前年になされている。
モーツァルトの作品の中で、特に最後の3大交響曲は指揮者にとっては避けて通ることのできない、その指揮者の音楽の本質的なところを明らかにし得るという点に於いても極めて重要なレパートリーであろう。フルトヴェングラーが第二次世界大戦後に至るまでのベルリン・フィルの定期演奏会でプログラムに取り上げたモーツァルトの交響曲は、「プラハ」以降の4曲に限られているが、その中で「ジュピター」は、1929年2月のただ1回(2日間)だけである。それに対して第39番と「ト短調」は、いずれも4回以上で「ト短調」が最も多く、しかも戦後取り上げた唯一のモーツァルトの交響曲ともなっている。
その演奏は速い速いといわれて来たが、モーツァルトの「ト短調交響曲」の代表的名盤として多くの人びとによって挙げられてきたのが、フルトヴェングラーとウィーン・フィルによる録音であるのは興味深いことである。打算を加えれば、オリジナル楽器派の演奏が主流になった今、その先見性が改めて評価されるべき時にもなろう。まるで地煙りをたてながら疾駆しているような激越な第1楽章。〈モルト・アレグロ〉の指示に従っている点で傾聴に値する。悲劇的情感を振り撒く瞬間瞬間の“音”である。恐らくモーツァルトが目指していたであろう孤独感、寂寥感を誰よりも速いテンポで再現した。それでいて品格を失うことがない。このテンポだからこそ可能だった表現であるし、フルトヴェングラーが指揮するウィーン・フィルの美音だからこそ音楽的な素晴らしさが保てたのだ。
よくこの演奏を「せかせかしている」と批判する方もいるが、「疾走する悲しみ」という観念的理解を持たせて余りある。50年代のウィーン・フィルならではの甘美なポルタメントも味わえるし、低弦の音もインパクトがあり、一度聴いたら忘れられない感触を残すワルターをはじめ、同時代の指揮者の「ト短調交響曲」とはフルトヴェングラーの解釈は一線を画す。フルトヴェングラーは、この曲からロマン主義的な懐古の情を排除した。あるのは刹那的な無常観である。
先輩格のニキッシュから習得したという指揮棒の動きによっていかにオーケストラの響きや音色が変わるかという明確な確信の元、自分の理想の響きをオーケストラから引き出すことに成功していったフルトヴェングラーは、次第にそのデモーニッシュな表現が聴衆を圧倒する。当然、彼の指揮するオペラや協奏曲もあたかも一大交響曲の様であることや、テンポが大きく変動することを疑問に思う聴衆もいたが、所詮、こうした指揮法はフルトヴェングラーの長所、特徴の裏返しみたいなもので一般的な凡庸指揮者とカテゴリーを異にするフルトヴェングラーのキャラクタとして不動のものとなっている。全く機械的ではない指揮振りからも推測されるように、楽曲のテンポの緩急が他の指揮者に比べて非常に多いと感じます。しかし移り変わりがスムーズなため我々聴き手は否応なくその音楽の波に揺さぶられてしまうのである。
「バッハの演奏は難しい。私自身が神になる必要があるからね。しかし、ブラームスやワーグナーは地のままでいけば良いのだ。」と語ったフルトヴェングラーは、モーツァルトにも同じことを感じていたのかもしれない。モーツァルトの音楽は深い内容を備えているが、それは分かる人には分かる式のもので説明調になったり強調してはならないのである。またフルトヴェングラーは「形式は明確でなければならない。すっきりと枯れていて、決して余分なものがあってはならない。」と語っていたが、その言葉の全き実践がこのモーツァルトであり音楽の哀しみの中に身をもって入り込み痛切に嘆きつくしている。「ト短調交響曲」を内面的には少しも抑制しない、フルトヴェングラーの魂の告白は異常なほどだが、厳しくも混じり気のない造型が大きな力となって、素晴らしい透徹感を生んでいる。
フルトヴェングラーの音楽を讃えて、「音楽の二元論についての非常に明確な観念が彼にはあった。感情的な関与を抑制しなくても、構造をあきらかにしてみせることができた。彼の演奏は、明晰とはなにか硬直したことであるはずだと思っている人がきくと、はじめは明晰に造形されていないように感じる。推移の達人であるフルトヴェングラーは逆に、弦の主題をそれとわからぬぐらい遅らせて強調するとか、すべてが展開を経験したのだから、再現部は提示部とまったく変えて形造るというような、だれもしないことをする。彼の演奏には全体の関連から断ち切られた部分はなく、すべてが有機的に感じられる。」とバレンボイムの言葉を確信しました。これが没後半世紀を経て今尚、エンスーなファンが存在する所以でしょう。
戦後のスタジオ録音はフルトヴェングラーの録音の中では音が良い。 ― 一概にフルトヴェングラーの音が悪いというのは、演奏された響きに対して録音の響きが浅いのだ。 ― フルトヴェングラーの EMI 録音のなかではウィーン楽友協会でセッション録音された本盤が、録音条件や演奏の質の高さから言ってもフルトヴェングラーの奥義を刻印した格調高いモーツァルト演奏だ。敵前逃亡を決意したフルトヴェングラーにとって、死の匂いのする寂寥と結晶化した悲哀こそ、この曲の本質であるべきだった。
この演奏の醍醐味は、いたずらに甘ったるい感傷を求めない高潔な精神、前へ前へと進む動的なテンポによって曲の持つ悲劇性が自ずと浮かび上がり、崇高な気分を宿していることをせかせかと急き立てるような第1楽章のテンポに聴くことだ。
その演奏は速い速いといわれて来たが、モーツァルトの「ト短調交響曲」の代表的名盤として多くの人びとによって挙げられてきたのが、フルトヴェングラーとウィーン・フィルによる録音であるのは興味深いことである。打算を加えれば、オリジナル楽器派の演奏が主流になった今、その先見性が改めて評価されるべき時にもなろう。まるで地煙りをたてながら疾駆しているような激越な第1楽章。〈モルト・アレグロ〉の指示に従っている点で傾聴に値する。悲劇的情感を振り撒く瞬間瞬間の“音”である。恐らくモーツァルトが目指していたであろう孤独感、寂寥感を誰よりも速いテンポで再現した。それでいて品格を失うことがない。このテンポだからこそ可能だった表現であるし、フルトヴェングラーが指揮するウィーン・フィルの美音だからこそ音楽的な素晴らしさが保てたのだ。
よくこの演奏を「せかせかしている」と批判する方もいるが、「疾走する悲しみ」という観念的理解を持たせて余りある。50年代のウィーン・フィルならではの甘美なポルタメントも味わえるし、低弦の音もインパクトがあり、一度聴いたら忘れられない感触を残すワルターをはじめ、同時代の指揮者の「ト短調交響曲」とはフルトヴェングラーの解釈は一線を画す。フルトヴェングラーは、この曲からロマン主義的な懐古の情を排除した。あるのは刹那的な無常観である。
先輩格のニキッシュから習得したという指揮棒の動きによっていかにオーケストラの響きや音色が変わるかという明確な確信の元、自分の理想の響きをオーケストラから引き出すことに成功していったフルトヴェングラーは、次第にそのデモーニッシュな表現が聴衆を圧倒する。当然、彼の指揮するオペラや協奏曲もあたかも一大交響曲の様であることや、テンポが大きく変動することを疑問に思う聴衆もいたが、所詮、こうした指揮法はフルトヴェングラーの長所、特徴の裏返しみたいなもので一般的な凡庸指揮者とカテゴリーを異にするフルトヴェングラーのキャラクタとして不動のものとなっている。全く機械的ではない指揮振りからも推測されるように、楽曲のテンポの緩急が他の指揮者に比べて非常に多いと感じます。しかし移り変わりがスムーズなため我々聴き手は否応なくその音楽の波に揺さぶられてしまうのである。
「バッハの演奏は難しい。私自身が神になる必要があるからね。しかし、ブラームスやワーグナーは地のままでいけば良いのだ。」と語ったフルトヴェングラーは、モーツァルトにも同じことを感じていたのかもしれない。モーツァルトの音楽は深い内容を備えているが、それは分かる人には分かる式のもので説明調になったり強調してはならないのである。またフルトヴェングラーは「形式は明確でなければならない。すっきりと枯れていて、決して余分なものがあってはならない。」と語っていたが、その言葉の全き実践がこのモーツァルトであり音楽の哀しみの中に身をもって入り込み痛切に嘆きつくしている。「ト短調交響曲」を内面的には少しも抑制しない、フルトヴェングラーの魂の告白は異常なほどだが、厳しくも混じり気のない造型が大きな力となって、素晴らしい透徹感を生んでいる。
フルトヴェングラーの音楽を讃えて、「音楽の二元論についての非常に明確な観念が彼にはあった。感情的な関与を抑制しなくても、構造をあきらかにしてみせることができた。彼の演奏は、明晰とはなにか硬直したことであるはずだと思っている人がきくと、はじめは明晰に造形されていないように感じる。推移の達人であるフルトヴェングラーは逆に、弦の主題をそれとわからぬぐらい遅らせて強調するとか、すべてが展開を経験したのだから、再現部は提示部とまったく変えて形造るというような、だれもしないことをする。彼の演奏には全体の関連から断ち切られた部分はなく、すべてが有機的に感じられる。」とバレンボイムの言葉を確信しました。これが没後半世紀を経て今尚、エンスーなファンが存在する所以でしょう。
戦後のスタジオ録音はフルトヴェングラーの録音の中では音が良い。 ― 一概にフルトヴェングラーの音が悪いというのは、演奏された響きに対して録音の響きが浅いのだ。 ― フルトヴェングラーの EMI 録音のなかではウィーン楽友協会でセッション録音された本盤が、録音条件や演奏の質の高さから言ってもフルトヴェングラーの奥義を刻印した格調高いモーツァルト演奏だ。敵前逃亡を決意したフルトヴェングラーにとって、死の匂いのする寂寥と結晶化した悲哀こそ、この曲の本質であるべきだった。
この演奏の醍醐味は、いたずらに甘ったるい感傷を求めない高潔な精神、前へ前へと進む動的なテンポによって曲の持つ悲劇性が自ずと浮かび上がり、崇高な気分を宿していることをせかせかと急き立てるような第1楽章のテンポに聴くことだ。
本盤は1951年1月ウィーン、ムジークフェラインザールでのセッション録音。
通販レコード詳細・コンディション、価格
Wilhelm Furtwängler - W.A. Mozart - Symphony No. 40 in G minor K. 550 / Serenade No. 13 in G Major K. 525 "Eine Kleine Nachtmusik"
- レコード番号
- HA1018
- 作曲家
- ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト
- オーケストラ
- ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団
- 指揮者
- ヴィルヘルム・フルトヴェングラー
- 録音種別
- MONO
東芝音楽工業前身東京芝浦電気謹製(金文字), MONO 1枚組 フラット重量盤210g。1960年代初頭リリース・当時の「東芝音楽工業株式会社」製レコードは丁寧な造りで英国直輸入スタンパー使っていた所為か高音質なものが多い。1960年代前半のフラット盤は音圧が強くサーフェスノイズこそ弱音部に少し認識しますが、時代勘案しても状態は良好です。
- ジャケット状態
- M-
- レコード状態
- EX++
- 製盤国
- JP(日本)盤
通販レコード
詳細の確認、購入手続きは品番のリンクから行えます。| オーダーは | 品番 / 34-24392 |
| 販売価格 | 5,000円(税別) |
通販レコードの購入にあたって・確認とお問い合わせは
プライバシーに配慮し、会員登録なしで商品をご購入いただけます。梱包には無地のダンボールを使用し、伝票に記載される内容はお客様でご指定可能です。郵便局留めや運送会社営業所留めの発送にも対応しております。入手のメインルートは、英国とフランスのコレクターからですが、その膨大な在庫から厳選した1枚1枚を大切に扱い、専任のスタッフがオペラなどセット物含む登録商品全てを、英国 KEITH MONKS 社製マシンで洗浄し、当時の放送局グレードの機材で入念且つ客観的にグレーディングを行っております。明確な情報の中から「お客様には安心してお買い物して頂ける中古レコードショップ」をモットーに運営しております。
.
https://fm-woodstock.com
通販サイトで毎日入荷、販売しています。

初期盤・クラシックレコード専門店「RECORD SOUND」

セクシーランジェリー・下着 通販専門店「Berry Berry」

アダルトDVD 通信販売 専門店 adultmedia(アダルトメディア)
商品検索
【500円均一】細菌、飛沫ウイルスなど空気中の微細物質を防ぐ ― 抗菌や防塵に効果的な三層構造の不織布サージカルマスク
ピアノが好きな人なら是非とも持っておくべき一枚◉ウラディーミル・ホロヴィッツ◯ホロヴィッツ・イン・モスコー
【歴史的音盤】反復を敢行した最初の録音◉メンゲルベルク指揮ニューヨーク・フィル◯ベートーヴェン・交響曲3番《英雄》
音楽全体を流れるエネルギーが強烈◉臨場感 フルトヴェングラー指揮ウィーン・フィル モーツァルト・「ドン・ジョヴァンニ」
【500円均一】細菌、飛沫ウイルスなど空気中の微細物質を防ぐ ― 抗菌や防塵に効果的な三層構造の不織布サージカルマスク
オーディオの拘り甲斐を感じる*ミルシテイン スタインバーグ指揮ピッツバーグ響 ベートーヴェン・ヴァイオリン協奏曲
ピアノが好きな人なら是非とも持っておくべき一枚◉ウラディーミル・ホロヴィッツ◯ホロヴィッツ・イン・モスコー
【歴史的音盤】反復を敢行した最初の録音◉メンゲルベルク指揮ニューヨーク・フィル◯ベートーヴェン・交響曲3番《英雄》
音楽全体を流れるエネルギーが強烈◉臨場感 フルトヴェングラー指揮ウィーン・フィル モーツァルト・「ドン・ジョヴァンニ」
【500円均一】細菌、飛沫ウイルスなど空気中の微細物質を防ぐ ― 抗菌や防塵に効果的な三層構造の不織布サージカルマスク
オーディオの拘り甲斐を感じる*ミルシテイン スタインバーグ指揮ピッツバーグ響 ベートーヴェン・ヴァイオリン協奏曲
名盤,魅力,アナログレコード,通販,熊本地震
コメントを表示されたくない時はコメントに明示してください。